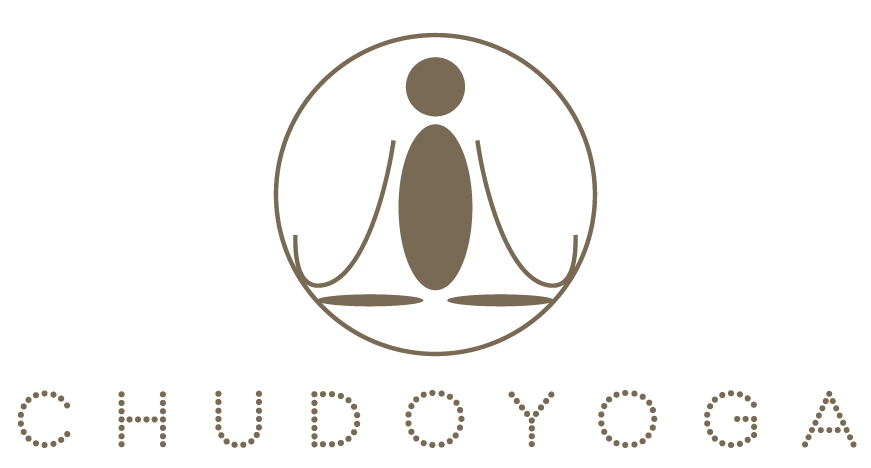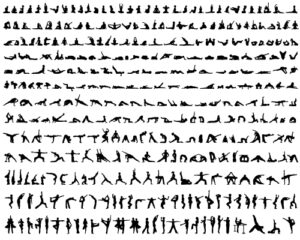ハタヨーガとは?
- ハタヨーガは別名、ハタ・ヴィディヤー(ハタの科学)といい、
より体にフォーカスした生理的ヨーガである。 - 「ハタ」とはサンスクリット語で、「力」、「強さ」、「忍耐」、「努力」の意、
また「ハタ」の「ハ」は太陽、つまり陽のエネルギー、
「タ」は月、つまり陰のエネルギーという別解釈も存在する。
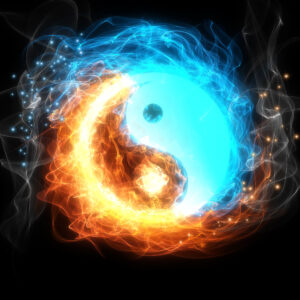
- ハタヨーガは8-9世紀ころに徐々に形成され、
12-13世紀以降に「ハタヨーガ」と呼ばれる体系にまとめられる。 - ハタヨーガは心の働きの止滅というよりも「心の働きの統御」をめざし、
古典ヨーガ(ラージャヨーガ)よりもいっそう精神生理学的、
肉体的な修練に重点をおいている。 - 13世紀になるとハタヨーガの開祖といわれるゴーラクシャ(ゴーラクナート)が「ハタヨーガ」、
「ゴーラクシャ・シャタカ」を記す。
前者は現存しておらず、後者はわずか101頌(1頌は32音節から成る韻文)からなる
簡潔でハタヨーガ最古の文献。 - 16世紀ころにスヴァートマーラーマによって「ハタヨーガ・プラディーピカー」があらわされ、
ハタヨーガを体系的に説明した。
それ以外は、ゲーランダによるハタヨーガの解説書「ゲーランダ・サンヒター」、
「シヴァ・サンヒター」がある。 - ハタヨーガの根本経典である、「ハタヨーガ・プラディーピカー」の内容は整然と構成されており、
第一章アーサナ(体位法)、第二章プラーナヤーマ(調息法)、第三章ムドラー(印相)、
第四章サマーディ(三昧)という四章に分かれている。 - サーンキヤ哲学に基づいた古典ヨーガでは、
プラクリティ(根本原質)の活動を止滅させることによって
プルシャ(霊我)を顕現させるものであったが、
ハタヨーガにおいても、この現象世界を死滅させることによってブラフマン(梵)に到達する、
つまり大宇宙と小宇宙の合一を目指している。
ハタヨーガ・プラディーピカー
- 「ハタヨーガ・プラディーピカー」は
16世紀ころにスヴァートマーラーマによって著されたハタヨーガの根本経典。
プラディーピカーとは「灯明」の意味。
「ハタヨーガ・プラディーピカー(ハタヨーガ)の灯明」は明確に体系を記述している。 - サマーディに融合したヨーガ行者は、寒暑を区別せず、同様に楽がなく、苦がなく、また、名誉がなく、不名誉もない。(4:111)
- ラージャヨーガを知らないで、もっぱらハタヨーガだけを行ずる者たちは努力の果実を失くした者たちであると考えられる。(4:79)
- この文献は全4章、400ほどの韻文から成る。
それらはハタヨーガの重要な諸観念やテクニックがほぼ網羅されており、
第一章アーサナ(体位法)、第二章プラーナヤーマ(調息法)、
第三章ムドラー(印相)、第四章サマーディ(三昧)という四章に分かれている。
第一章では禁戒、勧戒を経てアーサナへ進み、第二章ではプラーナヤーマと
「シャット・カルマ(6つの浄化法)」、第三章ではムドラーと「バンダ(固定)」を取扱い、
第四章ではラージャヨーガが解説されている。 - 多数の教説で混乱する暗闇で、ラージャヨーガを知らない人々に、憐れみ深いスヴァートマーラーマは、ハタの灯りをともす(ハタの解説を示す。)(1:3)
- アーサナが堅固になってから、ヨーガ行者は、自己を抑制し、有益で適量の食事を摂り、師に指示された方式に則り、プラーナヤーマを修するべきである。(2:1)
- 脂肪、カパの過剰の者は、予め6種(ダウティ、ヴァスティ、ネーティ、トラータカ、ナウリ、カパーラバーティ)の行法を行うべきである。しかし他の者は、ドーシャが均質であるゆえに、それらを行うべきではない。(2:21)